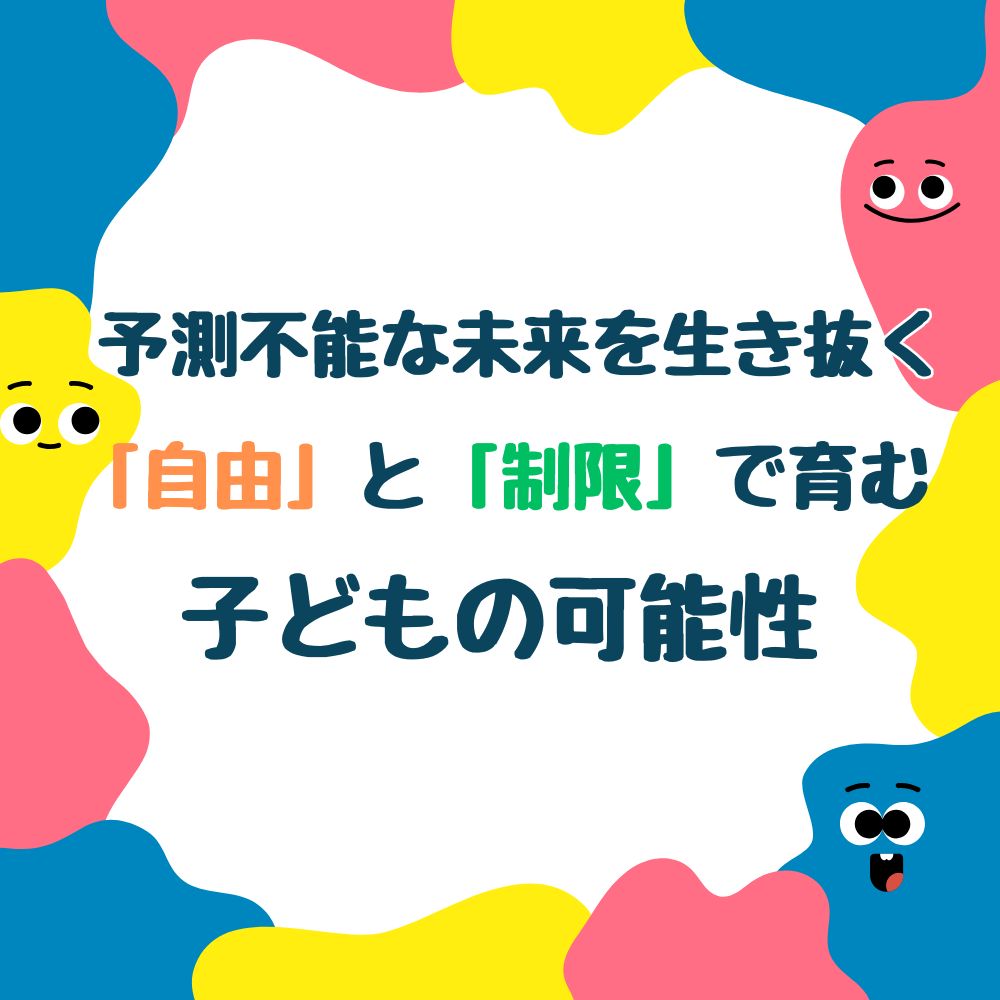「好きなことを思い切りやらせてあげたい」
「“やりたい放題” にしたら将来困るかもしれない」
変化が激しい現代。
「子育てって、一体なにが“正解”なの?」そんな方もいらっしゃると思います。
自由を尊重すれば、才能が花開く期待がある一方で、規律を教えなければ社会でつまずくのでは?という不安…。
かつて自分が味わった後悔や願望を子どもに投影してしまう瞬間もあるでしょう。
本記事では、「自由」と「制限」をどうバランスさせるかを具体的に考えます。
「わが家はこうしてみよう!」と一歩踏み出せるヒントにしてみてください。
1.「やりたい!」をとことん追いかける子が手にする3つの宝物
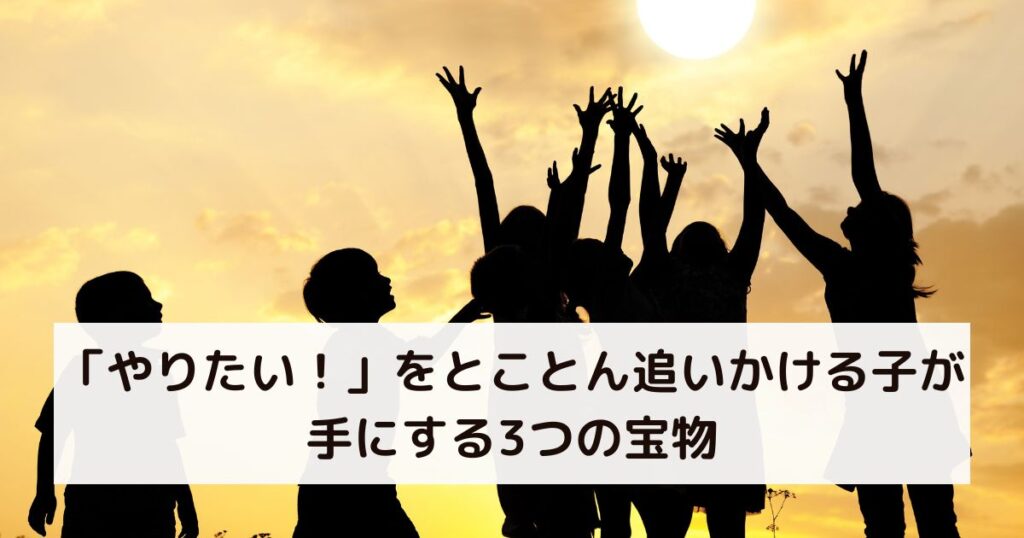
自分の内なる声に耳を傾け、「好き」や「楽しい」を追求する子どもたち。
子どもたちは好奇心に満ちあふれ、失敗を恐れずに挑戦するエネルギーを持っています。
以下では、「やりたいこと」を追求する子どもが手にする3つの宝物を紹介します。
1-1.主体性と自己肯定感
自分で選び、行動することで、「自分にはできる」という感覚や、ありのままの自分を受け入れる心が育まれます。
これらは、困難に立ち向かい、人生を切り拓くための重要な土台となるでしょう。
そんな主体性をもった探究心は、一生ものの学ぶ力を育てます。
1-2.探求心と創造性
「なぜ?」「もっと知りたい」という探求心は、学びを深め、既存の枠にとらわれない新しい発想や創造性を生み出す原動力となります。
今、話題のAIは既存のものを出力するのに長けていますが、この領域は苦手とされています。
そのため、子どもの時に「やりたいこと」を追求し、創造的な時間を過ごした経験は、これからの時代を生きる際に大きな財産となる期待が持てます。
また、やりたいことを通じて出会う仲間とのコミュニケーションは、社会性を育むことも期待できるでしょう。
1-3.内発的動機づけ
「やらされる」のではなく「やりたいからやる」という内側から湧き出るエネルギーは、持続力があり、困難な状況でも粘り強く取り組む力に繋がります。
しかし、「自由」には責任が伴います。
好きなことだけを追い求め、努力や忍耐、他者との協調を学ばなければ、社会の中で孤立したり、壁にぶつかった時に乗り越えられなくなったりする可能性も…。
「自由」を本当の力に変えるためには、ただ放任するのではなく、適切な見守りや、時には軌道修正、そして失敗から学ぶ機会を与えるサポートが不可欠です。
2.制限が多い環境で育つ子が身につける3つの土台
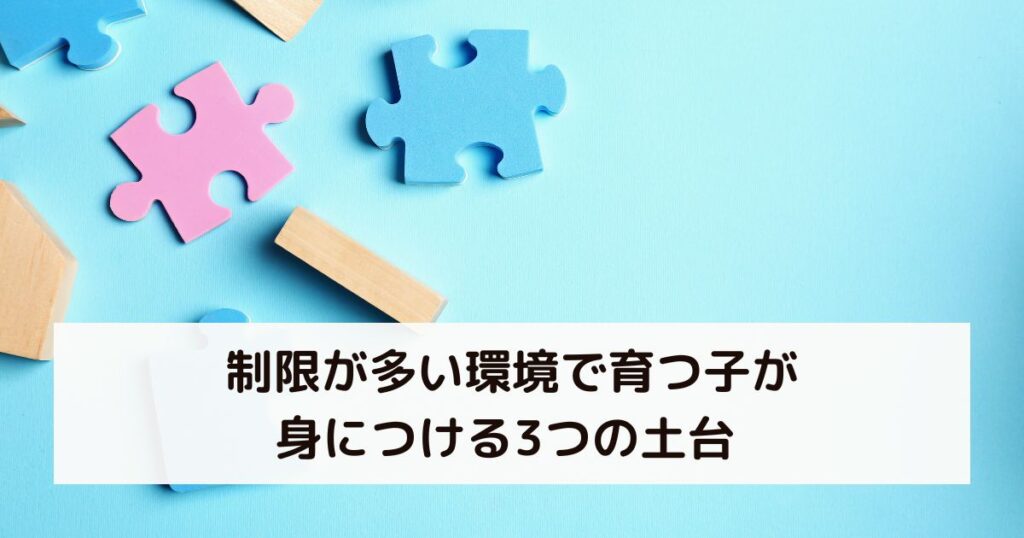
一方、ルールや規律、やるべきことを教えられ、ある程度の「制限」の中で育つ子どもたちもいます。
一見、窮屈そうに見えるかもしれませんが、そこにはまた別の力が育まれる可能性があります。
以下では、制限に期待できる3つの土台を紹介します。
2-1.規律と忍耐
時間を守る、目標に向かって努力する、衝動をコントロールするといった力は、社会生活を送る上で欠かせません。
具体的には下記のとおりです。
- ゲームは一日〇時間まで
- すぐに成果が出なくてもコツコツと続ける
- 遊びたい気持ちを抑えて片付けをする
これらの力は、目標達成や自己管理能力の基礎となることが期待できます。
2-2.協調性
ルールを守り、他者との関わりの中で自分の欲求を調整することを学ぶことで、円滑な人間関係を築く力が育まれます。
具体的には下記のとおりです。
- 公園の遊具を順番に使う
- 友達との意見の衝突
- 困っている友達を助ける
これらは、協調性を育む力となることが期待できます。
2-3.集中と計画性
限られた時間や条件の中で課題に取り組む経験は、集中力や計画性を養い、効率的に物事を進める力を高めます。
- 〇分間は集中して勉強する
- テスト前に勉強の計画を立てる
- 限られたお小遣いを計画的に使う
しかし、過度な「制限」や一方的な押し付けは、子どもの可能性を潰しかねません。
また常に指示されたことだけを行うことに慣れてしまうと、自分で考え、行動する力が育ちにくくなります。
「自分のやりたいこと」が分からなくなってしまうケースも少なくないでしょう。
その他、親の期待に応えられない自分を責めたり、常に評価を気にしたりすることで、自己肯定感が低くなってしまうことがあります。
「こうあるべき」という枠に縛られ、自由な発想やチャレンジ精神が失われてしまう可能性もあります。
「我が家のルールって、ちょっと厳しいのかな…」と不安になる方もいらっしゃると思います。
そんな場合は、「夫婦で話し合う」「友達に相談する」など、第三者からの意見を聞いてみるのも良いかもしれません
3.「自由」と「規律」のバランスが大事!
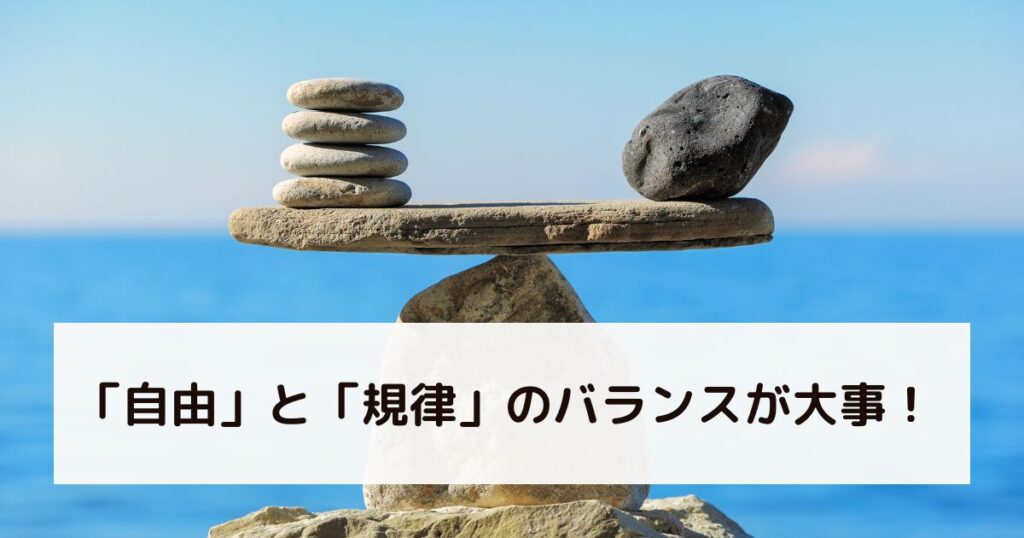
結局のところ、「やりたいことをさせる」ことと「制限する」ことは、どちらか一方を選ぶといった、1か100で考えるべきではありません。
大切なのは、その子の個性や発達段階に合わせて、「自由」と「規律」のバランスを柔軟に取っていくことです。
また、「制限」と感じるものの中にも、子ども自身が納得し、選択できる要素を取り入れる工夫が必要です。
「なぜ、そのルールが必要なのか?」を丁寧に伝え、話し合う。
いくつかの選択肢の中から自分で選ばせる。
そうすることで、子どもは「やらされている」のではなく、「自分で決めた」と感じ、主体的に規律を学ぶことができます。
そのためには、お父さんお母さんも子どもに伝わるように言語化する必要があるでしょう。
4.親自身も不安と向き合う
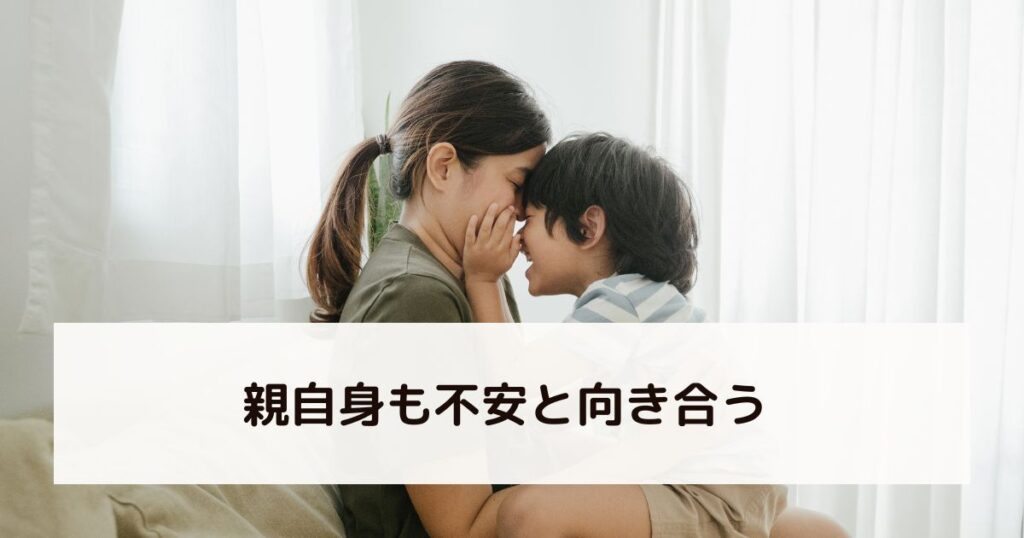
この「自由」と「制限」のバランスに悩むとき、親御さん自身が心の中にある不安や価値観が影響していることもあるのではないでしょうか。
- 自分が育ってきた環境
- 社会からのプレッシャー
- 漠然とした将来への不安
上記を含め、まずは、自分自身が何に不安を感じ、何を本当に願っているのかを見つめ直すことが大切です。
そして、完璧な「正解」を求めすぎず、子どもと共に試行錯誤していくプロセスそのものを大切にしてみても良いのかもしれません。
子どもとの対話を重ね、その子の「好き」という小さな芽を大切に育みながら、社会で生きていくための知恵や力を授けていく。
それは、根気と愛情が必要な、しかし何物にも代えがたい物と感じます。
未来は誰にも予測できません。
だからこそ、どんな状況になっても、自分で考え、しなやかに乗り越え、自分らしい幸せを見つけられる人に育ってほしい。
そのために、できることは、子どもの可能性を信じ、しっかり支える土台をつくり、時にはそっと背中を押してあげることなのかもしれません。
まとめ
これからの未来がどうなるのか、誰にも正確に予測することはできません。
だからこそ、どんな時代、どんな状況になったとしても、子どもたちが自分で考え、困難をしなやかに乗り越え、自分らしい幸せを見つけられる人に育ってほしい。
そのために私たち親ができることは、子どもの可能性を心から信じ、いつでも帰ってこられる安心できる土台となり、そして、新しい一歩を踏み出そうとするときには、そっと背中を押してあげることなのかもしれません。
以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございます。