「周りの子はみんな持っているのに、うちの子だけ持たせないのは可哀想?」
「スマホに夢中になって勉強しなくなったら、どうしよう…」
「家でスマホばかり触っているけど大丈夫かな…」
そんな不安が尽きない方もいらっしゃると思います。
この記事では、子どもの年齢別スクリーンタイム(スマホなどの画面を見る時間)の目安をご紹介!
スマホの長時間使用が引き起こす可能性のある「心と脳」「身体」「学習」「人間関係」への4つの具体的な弊害を詳しく解説します。
また、今日から家庭で実践できる「3つの具体的な対処法」についても分かりやすくお伝えします。
スマホとの付き合い方の参考になると思いますので、ぜひご覧ください。
1.スマホの推奨される使用時間は?
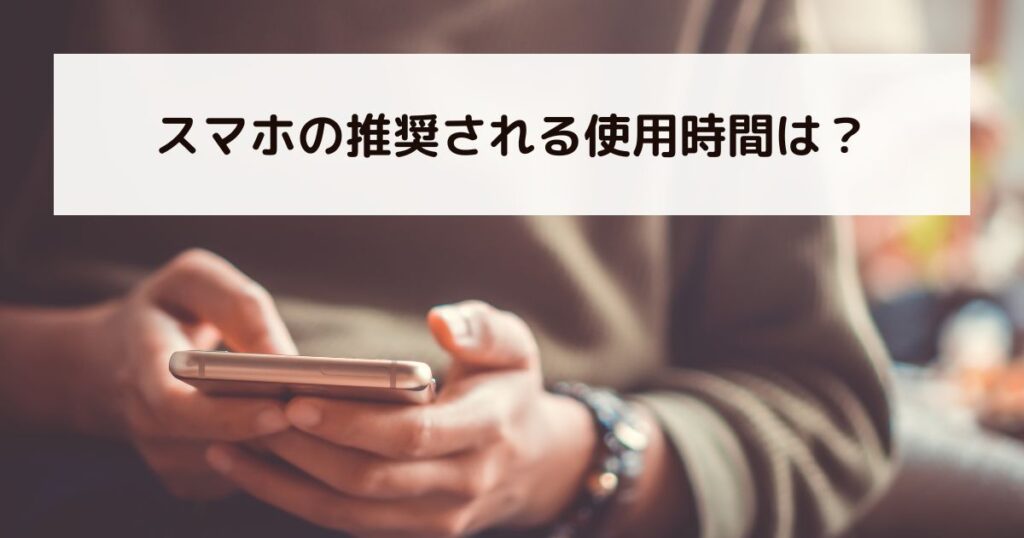
以下、0~5歳までの推奨スクリーンタイムに関する表です。
| 年齢区分 | 推奨されるスクリーンタイム (画面を見る時間) | 特に気をつけたいこと・ポイント |
|---|---|---|
| 0歳 ~ 2歳未満 | 基本的には推奨されない | ・画面を見るよりも、人との触れ合いや、おもちゃで遊ぶなどの実体験が 発達にはるかに重要とされる。 |
| 2歳 ~ 5歳 (幼児) | 1日合計 1時間以内 (より少ない方が望ましい) | ・見る場合は、教育的な番組など「質の高い内容」を選びましょう。 |
成人の場合でも3時間以内を推奨される内容が多く見受けられました。
スマホの使用時間が、これらの推奨時間より多い場合は、以下の弊害を引き起こす可能性があります。
2.スマホが子どもに及ぼす弊害【4つのカテゴリー別】
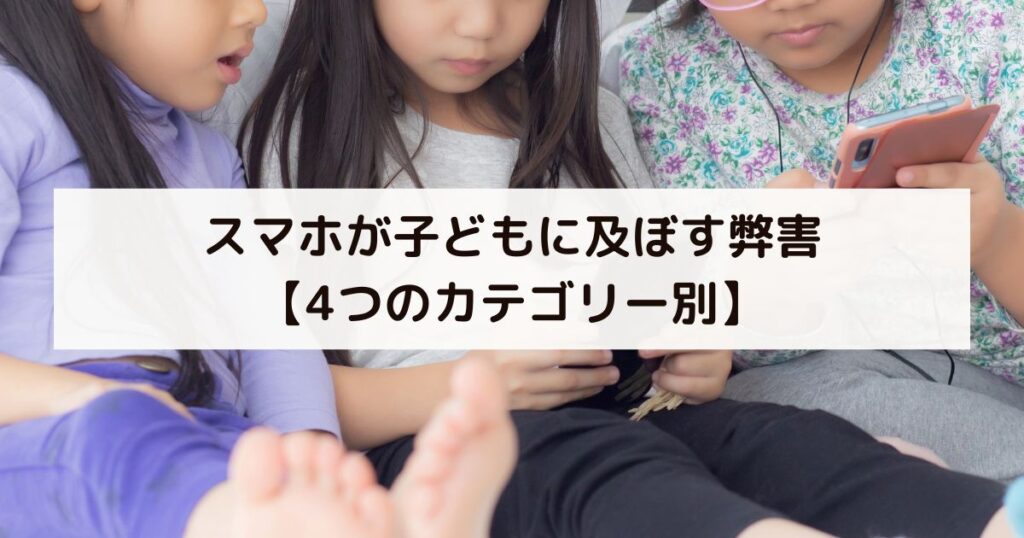
ここでは、スマホが子どもに及ぼす可能性のある主な弊害を、下記4つのカテゴリーに分けて解説してまいります。
- 心と脳への影響
- 身体への影響
- 学習・知的好奇心への影響
- 人間関係・社会性への影響
以下でそれぞれ解説してまいります。
2-1.心と脳への影響
「スマホ依存」
次々に流れてくる情報、ゲームの報酬、SNSの「いいね!」…。
スマホは脳の快楽回路を刺激しやすく、気づかぬうちに「もっと見たい」「やめられない」という依存状態に陥ることがあります。
特に下記のサインは要注意です。
- 食事中も手放せない
- 注意されると激しく怒る
- 使用時間を偽る
- スマホ以外の活動に興味を示さなくなる
こういった依存は、子どもの意志の弱さだけではなく、脳の仕組みにも関係していることを理解しましょう。
そのため、感情論ではなく、スマホを使ってしまう環境を考え直した方が良いでしょう。
集中力・記憶力の低下
短い動画や次々切り替わる情報に慣れると、1つのことにじっくり取り組む集中力が低下する可能性があります。
また、すぐに検索して答えが見つかる便利さは、深く考えたり、情報を多角的に検討したり、記憶したりする機会を奪いかねません。
ちなみに、スマホの長時間利用による脳疲労を「スマホ認知症」と呼ぶことがあります。
これは、正式な病名ではなく、記憶力や集中力、言語機能などの低下が日常生活に支障をきたす状態を指します。
子どもだけでなく、大人もなりえるので注意しましょう。
SNS疲れ、自己肯定感の低下
SNS上で友だちの「キラキラした投稿」を見て自分と比較し、落ち込んだり、劣等感を抱いたりすることがあります。
「いいね!」の数に一喜一憂し、常に他者の評価を気にするようになることで、自己肯定感が揺らぎやすくなることも指摘されています。
また、ネット上の誹謗中傷に心を痛めたり、気分の浮き沈みが激しくなったりするケースも起こりえるでしょう。
2-2.身体への影響
睡眠不足・質の低下
夜遅くまでスマホを使用することで、寝る時間が遅くなりがちです。
また、画面から発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制し、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。
成長期の子どもにとって質の高い睡眠は、脳や身体の発達、記憶の定着、情緒の安定に不可欠。
睡眠不足は、日中の眠気や集中力低下だけでなく、長期的な健康問題にも繋がる可能性があります。
視力低下(スマホ老眼含む)、眼精疲労、ドライアイ
小さな画面を長時間見続けることは、目のピント調節機能を酷使し、近視の進行や、大人で言われる「スマホ老眼」(ピント調節が一時的にうまくいかなくなる状態)のような症状を引き起こす可能性があります。
また、まばたきの回数が減ることでドライアイになったり、眼精疲労から頭痛や肩こりを引き起こしたりすることも…。
ストレートネック、猫背、肩こり
スマホを見る際に、うつむいた姿勢を長時間続けることで、首の骨(頸椎)の自然なカーブが失われる「ストレートネック」になるリスクがあります。
これは首や肩のこり、頭痛、めまい、手のしびれなどを引き起こす原因にもなりかねません。
また、猫背など、全体的な姿勢の悪化にも繋がり、成長期の身体のバランスに影響を与える可能性があります。
2-3.学習・知的好奇心への影響
「ながら学習」による集中力の散漫
通知が気になったり、調べ物のつもりが動画を見てしまったり…。
スマホを傍らに置いた「ながら学習」は、集中力を著しく妨げます。
学習内容が深く理解できず、定着しにくくなる可能性があります。
受動的な情報収集による思考力・創造性の低下リスク
スマホを使えば、知りたい情報がすぐに手に入ります。
しかし、その情報が本当に正しいのか吟味したり、自分なりに解釈したり、複数の情報を組み合わせて新しいアイデアを生み出したりする「主体的な学び」の機会が減ってしまう可能性があります。
答えをすぐに見つけることに慣れると、粘り強く考える力が育ちにくくなるかもしれません。
知的好奇心の偏りと、リアルな学びの機会損失
興味のある分野の情報を深掘りできるメリットがある一方、アルゴリズムによって表示される情報が偏り、視野が狭くなる可能性もあります。
また、スマホに時間を費やすあまり、読書や自然体験、博物館訪問といった、五感を使ったリアルな学びの機会が失われてしまうことも懸念されるでしょう。
2-4.人間関係・社会性への影響
対面コミュニケーション能力の低下
家族や友だちと直接顔を見て話す時間が減ると、相手の表情や声色から感情を読み取ったり、場の空気を読んだり、言葉を選んで伝えたりする経験が不足しがちです。
そのため、非言語的なコミュニケーション能力が育ちにくくなる可能性があります。
ネットいじめ、仲間外れ、言葉の暴力のリスク
顔が見えない匿名の世界では、言葉が不用意に、そして残酷になることがあります。
SNSやメッセージアプリでのいじめ、仲間外れは、子どもの心を深く傷つけ、深刻な事態に発展しかねません。
また、自分自身が加害者になってしまうリスクも潜んでいます。
有害な情報との接触、知らない人との安易な繋がりのリスク
フィルタリングをしていても、意図せず暴力的なコンテンツや性的な情報、偏った思想などに触れてしまう可能性があります。
また、SNSなどを通じて見知らぬ人と簡単に繋がれるため、個人情報の漏洩や性被害、犯罪に巻き込まれるリスクもゼロではありません。
ちなみに、iPhone生みの親である「スティーブ・ジョブズ」は、自分の子どもたちに14歳になるまでスマートフォンを与えませんでした。
これは、彼自身がApple製品を開発しながら、子供たちが依存する可能性を懸念していたためといわれています。
3.スマホが子どもに及ぼす弊害への対処法
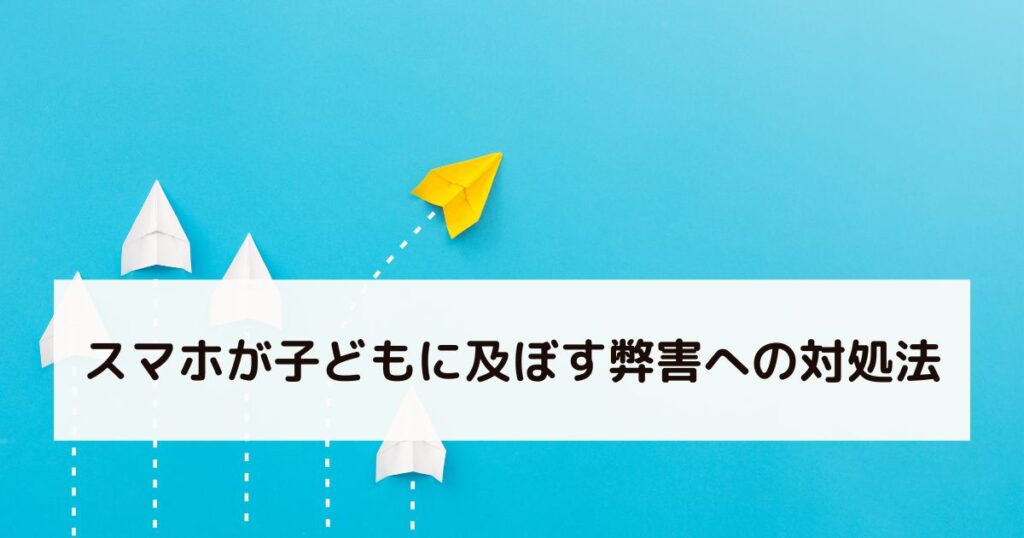
2章で紹介したように、スマホが子どもに及ぼす弊害は様々です。
そこで、こちらでは上記弊害への対処法を解説してまいります。
3-1.スマホの使用時間に制限を設ける
スマホ弊害を防ぎたい場合、使用時間に明確な制限を設けてみましょう。
ることです。
具体的な方法としては、「平日は夜9時まで」「1日の合計時間は2時間まで」といったルールを親子でしっかり話し合って決めることが挙げられます。
この時、「なぜ、その時間にするのか?」理由を伝え、お子さんの意見も聞くと、納得してルールを守りやすくなります。
タイマーを使ったり、スマホのスクリーンタイム機能を活用したりするのも有効です。
例えば、「この機能を使って、ゲームは1時間までにしよっか~」と親子で一緒に設定するのも良いでしょう。
3-2.スマホの通知をオフにする
次に、スマホからの不要な通知をオフに設定することも、集中力を守り、依存を防ぐために効果が期待できる対策です。
頻繁に届く通知は、せっかくの集中を簡単に中断させてしまうからです。
通知をオフにすることで、子ども自身が主体的にスマホと向き合う時間を選べるようになり、目の前の活動にしっかりと集中できる環境を作れます。
勉強時間や就寝時間など、特に集中したい時間帯は、スマホの「おやすみモード」や「集中モード」を活用し、一時的に全ての通知を遮断するのも有効な方法です。
3-3.デジタルデトックスを行う
意識的にスマホやデジタル機器から離れる時間「デジタルデトックス」を生活に取り入れることもスマホの弊害を受けない効果が期待できます。
デジタルデトックスは、その情報刺激から一時的に解放されることで、心と体をリフレッシュさせる効果があります。
また、スマホから目を離すことで、家族との会話を楽しんだり、読書や趣味に没頭したり、リアルな世界の豊かさを再発見するきっかけにもなります。
以下のような簡単なルールから始めてみるのも良いでしょう。
- 食事中は家族みんなスマホを置く
- 寝る前の1時間はリビングにスマホを置く
- 週末の午前中はスマホを使わない
また、親御さん自身が率先して取り組む姿を見せることで、お子さんにとっても良いお手本になります。
まとめ
今回は、子どものスマホ使用に関する推奨時間から、心身や学習、人間関係に及ぼす4つのカテゴリー別の弊害、そして家庭でできる3つの具体的な対処法まで詳しく解説しました。
スマホは現代社会において便利なツールである一方、使い方を誤ると、以下のように子どもの成長にとって見過ごせない様々なリスクがあることをご理解いただけたかと思います。
- スマホ依存
- 睡眠不足
- 視力低下
- 集中力低下
- コミュニケーション不足
しかし、過度に恐れる必要はありません。
大切なのは、これらのリスクを正しく理解したうえで、スマホに振り回されるのではなく、付き合い方を考え、メリハリを持って使うことだと感じます。
スマホの使用時間が多い場合は、「使用時間の制限」「通知オフ」「デジタルデトックス」といった対策を試し、付き合い方を工夫してみましょう。
ぜひ、この記事を参考に、ご家庭でできることから少しずつ始めてみてください。
■参考


