「なんだか最近、子どもの挨拶がぎこちないな…」と感じたことはありませんか?
「ありがとう」や「おはよう」がなかなか出てこないと、つい心配になってしまいますよね。
でも、それは子ども自身が「どう挨拶していいか分からない」サインかもしれません。
この記事では、幼稚園児から小学校低学年のお子さんが自然に挨拶できるようになるために、親としてどんな関わり方ができるのかをご紹介します。
ちょっとした工夫で、挨拶は習慣にできます。そして、その習慣はお子さんの「将来の人間関係」や「キャリア形成」にとって大きな財産になるはずです。
それでは、早速みていきましょう!
1章. 挨拶が大切な理由

挨拶は、心と心をつなぐ”入口”のようなもの。
大人同士でも、気持ちよく挨拶を交わせた日は、自然とその後の会話もスムーズにいきますよね。
それは子どもにとっても変わらないといえます。たとえ短い一言でも、相手に声をかけるという経験は、自己肯定感や信頼感につながっていきます。
また、挨拶を通じて「人と関わることへの安心感」や「自分から声をかけていいんだ」という感覚が育ちます。
そして何より一生モノのコミュニケーションスキルといえるでしょう。
2章. 挨拶が子どもの成長に与える4つの心理的効果
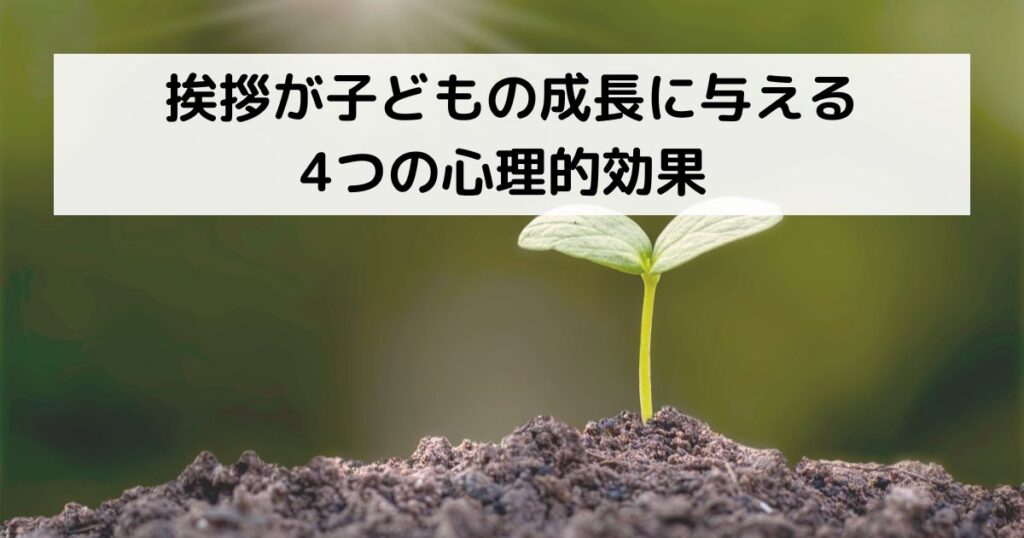
2-1. 自己肯定感が高まる
「おはよう」と言うと「おはよう」と返ってくる。
その小さなやりとりの中で、子どもは「自分は受け入れられた」と感じることができます。
それは、自己肯定感を支える大事な土台になります。
2-2. 社会性が育つ
挨拶は、人とのやりとりの”はじまり”です。
相手の存在を意識し、気持ちよく関わる経験を通して、相手を「思いやる気持ち」や「共感力」が自然と育まれていきます。
2-3. 気持ちの切り替えができるようになる
登園・登校時の「いってきます」や「おはよう」は、気持ちのスイッチを入れる合図にもなります。
毎日の繰り返しによって、子どもの中に安心できる”リズム”が生まれ、心の安定にもつながるでしょう。
2-4. コミュニケーションの土台になる
挨拶を通して、「人と関わる」ことに慣れていくと、人前で話すときの不安が軽くなったり、自分の気持ちを表現する力が自然と養われていきます。
3章. 親ができる”挨拶習慣”の3ステップ

3-1. まずは親が見本になる
子どもに「挨拶しなさい」と言うよりも、親が日常的に笑顔で挨拶している姿を見せることが一番の学びになります。
「おはよう」「ありがとう」「おかえり」
当たり前のようで、実はとても大切な一言。
それを親が自然に口にすることで、子どもも真似しやすくなるでしょう。
3-2. あらかじめ練習しておく
人前で話すのが苦手な子には、「誰に、どう言えばいいか」を事前に練習しておくと安心です。
例えば「明日、田中先生に会ったら”おはようございます”って言ってみようね。きっと先生も”おはよう”って笑顔で返してくれるよ」と、場面ごとにシミュレーションしておくと、子どももスムーズに行動できます。
お友達への挨拶なら「○○ちゃんに”おはよう”って言ってみる?一緒に遊べるかもしれないね」など、挨拶の後に起こる「楽しいこと」も一緒に想像させてあげると、挨拶が苦手な子どももハードルが下がるかもしれません。
3-3. 褒めてあげる
挨拶ができたときには、「言えたね」「気持ちよかったね」と声をかけてあげましょう。
その一言が「また言ってみようかな」という自信になります。
4章. 【年齢別】挨拶する時のコツ
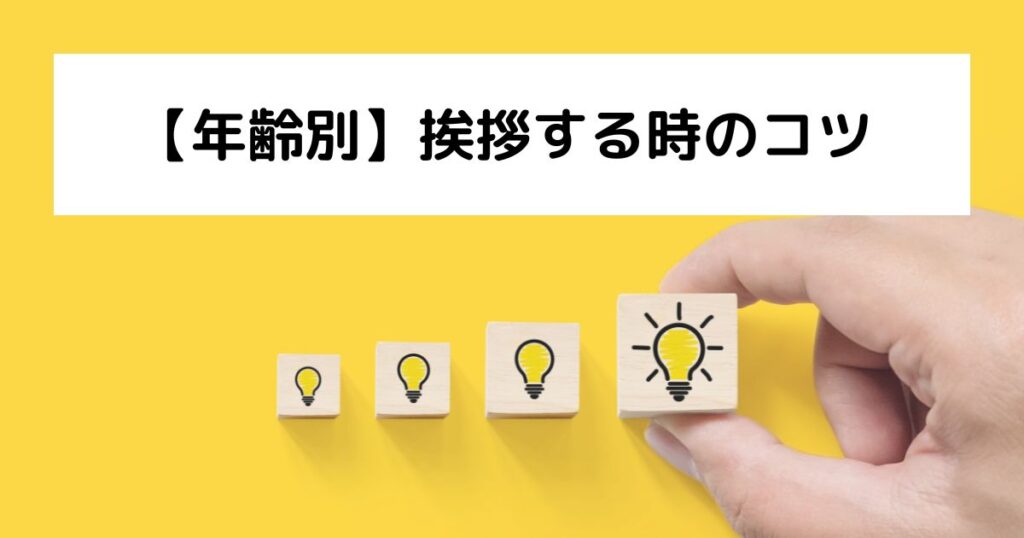
4-1.幼稚園児(3〜5歳)
この時期は、まず挨拶を「楽しいもの」として捉えてもらうことが大切です。
歌に合わせて「おはよ〜♪」と言ってみたり、手を振りながら「バイバイ」と言ったり、身体の動きと一緒に覚えると定着しやすくなります。
4-2.小学校低学年(6〜8歳)
少しずつ相手や場面に応じた挨拶を意識できるようになる時期です。
「先生には”おはようございます”、お友達には”おはよう”だね」と、使い分けを教えてあげましょう。
また、挨拶と一緒に「相手の目を見る」「笑顔でいる」といった要素も少しずつ加えていくと、より効果的なコミュニケーションが身につきます。
5章. 無理強いさせない声かけ&NG例
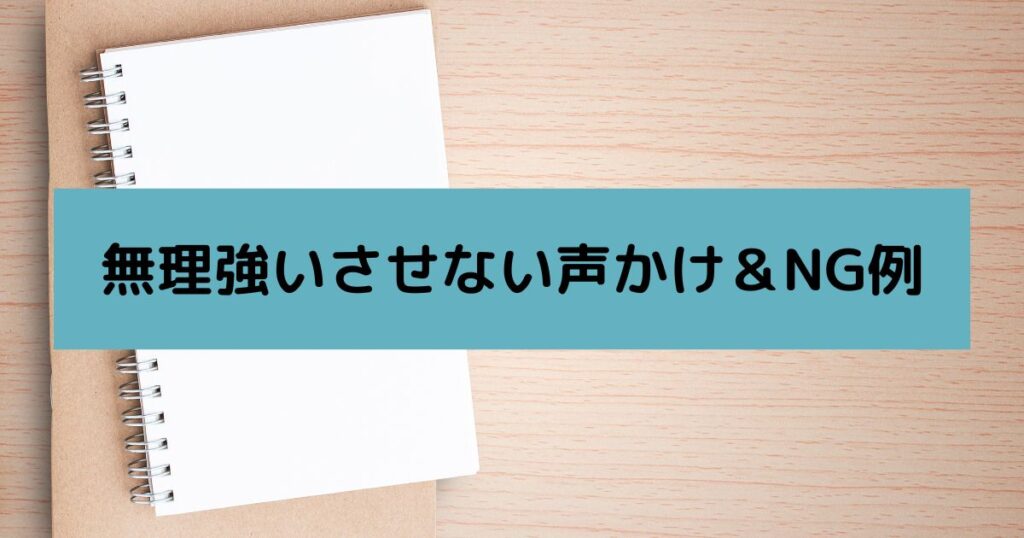
たとえ挨拶ができなかったとしても、「なんで言わないの?」と責めるのはNGです。
子どもにとって、挨拶はちょっぴり勇気がいること。
恥ずかしかったり、タイミングがわからなかったりするのは自然なことです。
そのため、責めるのではなく、「今日はちょっとドキドキしたかな?」と気持ちに寄り添ってあげることが大切です。
無理に言わせようとせず、子ども自身のペースを尊重してあげましょう。
6章. 長期視点で見た”挨拶習慣”の広がり
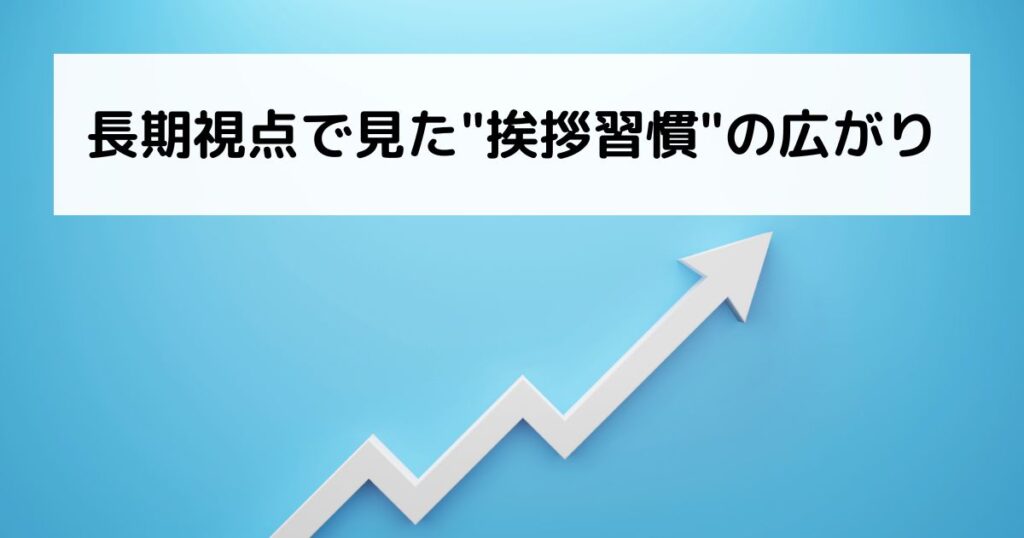
「挨拶ができる子」は、まわりからの信頼を得やすくなります。
幼稚園、小学校、そして社会に出たとき。
どんな人とも気持ちよく関わる力は、子どもの将来にとって「大きな武器」になります。
社会に出た場合ですと、以下のように挨拶力は様々な場面で活かされます。
- 就職面接での第一印象
- 職場での信頼関係構築
- プレゼンテーションでの聞き手との距離感
営業や接客業はもちろん、どんな職種でも「人と気持ちよく関われる人」は重宝される傾向がありますよね。
また、挨拶ができる人は「礼儀正しい」「協調性がある」「信頼できる」といった印象を与えやすく、昇進や重要なプロジェクトへの抜擢といったキャリアアップの機会にも恵まれやすくなります。
以上のように、挨拶は「将来の人間関係」や「キャリア」にも良い影響を与えてくれるといえるでしょう。
まとめ
挨拶は、小さな一歩。でもその一歩が、心を育て、関係を育て、未来をつくっていきます。
そんな未来のために、今日からできることはたった3つです。
①親が笑顔で挨拶する
②事前にシミュレーションしておく
③子どもが挨拶できたらしっかり褒める
無理に完璧を求めず、「できたこと」を一緒に喜ぶスタンスでOKです。
挨拶が自然にできるようになる頃、きっと子どもの心にも大きな変化が生まれているはずです。
以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。
■参考:
【子どもに教えたくなる】挨拶が大切な一番の理由【誰も教えていない】
あいさつで人生を豊かに!「あいさつ」できる子になる方法
挨拶の大切さを子どもに伝えよう!子どもが挨拶しない理由や親ができることをご紹介


