「目が疲れた…」
「しょぼしょぼする…」
「かすんで見えにくい…」。
パソコンやスマートフォンを長時間使用する現代人にとって、目の疲れは切っても切り離せない悩みですよね。
それと同時に「そのうち治るだろう」と放置している方もいらっしゃると思います。
しかし、目の疲れは進行すると「眼精疲労」となり、頭痛や肩こりといった全身の不調にもつながりかねません。
この記事では、「パソコンやスマホがなぜ目を疲れさせるのか?」そのメカニズムから、今日からできる簡単ケア、日頃の予防策、さらに目の機能そのものを鍛える「ビジョントレーニング」まで紹介します。
目の悩みを解決するための情報を網羅的にお届けしますのでぜひご参考ください。
1. そもそも、なぜ目は疲れるの?
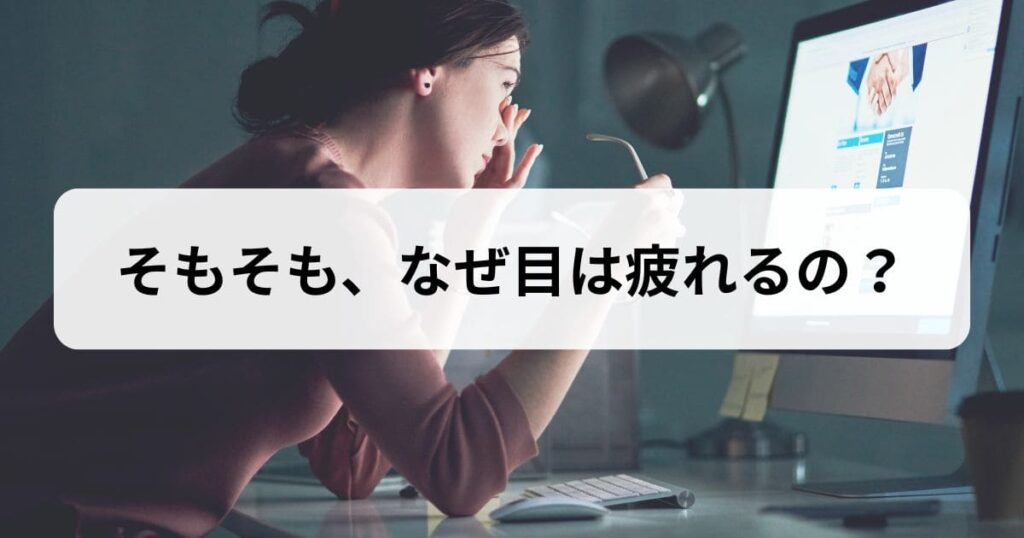
私たちの目は、デジタルデバイスの使用や姿勢など様々な要因で疲労が蓄積します。
以下で目の疲れとなる要因を解説します。
1-1. ブルーライトの正体と目への影響
スマートフォンやパソコン画面から発せられるブルーライトは、波長が短くエネルギーが強い光です。
これが網膜に達すると、ちらつきやノイズの原因となり、視覚的な負担となりかねません。
また、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制する影響も指摘されています。
太陽光にもブルーライトは多く含まれますが、デジタルデバイスからのブルーライトは、近距離で長時間浴びやすく、特に夜間は睡眠への影響も懸念されるため、注意が必要とされています。
1-2. 長時間作業で起こる「目の調節機能」の低下
画面に集中すると、ピントを合わせ続ける毛様体筋が常に緊張します。
この状態が続くと筋肉が凝り固まり、ピントが合いにくくなる「調節機能の低下」を引き起こしますと言われています。
これが、物がぼやけたり、ピントが合いにくくなったりする原因の一つです。
1-3. ドライアイが悪化する? 画面を見続けることの落とし穴
作業に集中すると、まばたきの回数が激減します。
通常1分間に約20回と言われるまばたきが数回になることで、目の表面が乾きやすくなり、ドライアイを悪化させます。
1-4. 姿勢や環境も目に影響
猫背で画面に顔を近づけすぎたり、照明が適切でなかったりする環境も目に余計な負担をかけます。
特に前かがみの姿勢は、首肩のコリを招き、結果として目の疲れをひどくさせる傾向があります。
2. 【今日からできる!】簡単セルフケアで目をリフレッシュ

目の疲れを感じたら、まずは手軽なセルフケアから始めてみましょう。
2-1. 効果的な休憩法:正しい休憩の取り方
デスクワークやスマホを使用する仕事の場合、長時間の連続作業は避け、定期的に休憩することをおすすめします。
理想は「1時間に10~15分程度」です。
目を閉じるだけでなく、遠くの景色を眺めることで、目のピント調節筋をリラックスさせましょう。
2-2. 温め・冷やしの効果的な活用法
蒸しタオルやホットアイマスクで目を温めると、血行促進や筋肉の緊張緩和に効果的です。
ただし、炎症や充血がある場合は、冷たいタオルなどで冷やす方が良い場合もあります。
仕事終わり、自宅でのリラックスタイムでは、目の状態に合わせて使い分けてみてください。
2-3. 簡単!目の体操&マッサージ
目の周りを軽く押したり、円を描くようにマッサージしたりすることで、血行を促進し、目の疲れを軽減できる効果が期待できます。
2-4. ツボ押しで血行促進!疲れが取れる「目」のツボ
目の内側のくぼみにある「睛明(せいめい)」や、眉毛の内側のくぼみにある「攢竹(さんちく)」などのツボを優しく押すと、目の周りの血行が促進され、リフレッシュ効果が期待できます。
2-5. 目薬の選び方・正しい使い方
充血や乾燥が気になる場合は、症状に合った目薬を選びましょう。
清涼感のあるものや保湿成分配合のものなど、様々な種類があります。
点眼時は清潔な手で行い、容器の先端が目に触れないように注意しましょう。
3. パソコン・スマホ利用時!目を疲れさせない予防策
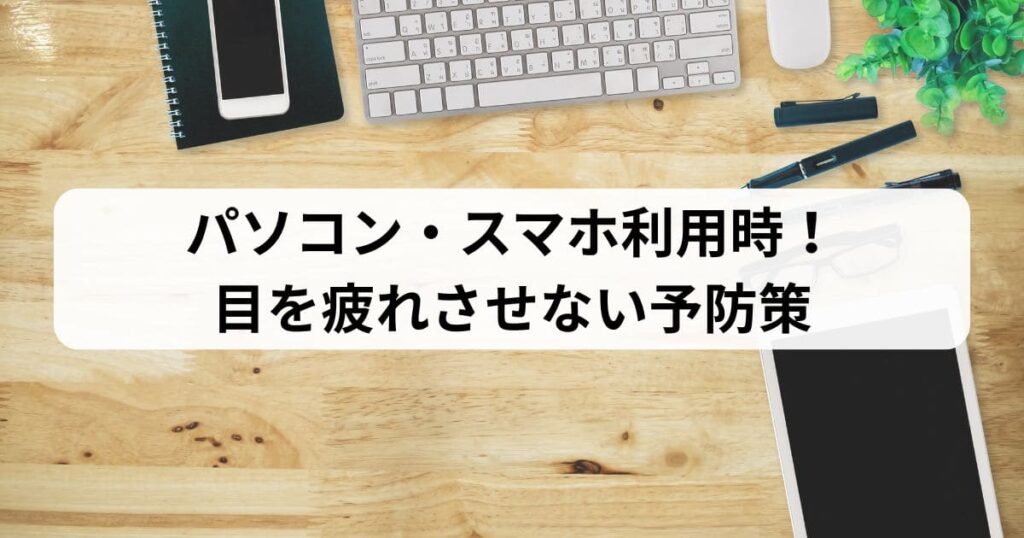
日頃のちょっとした工夫で、目の疲れを効果的に予防できます。
3-1. 画面設定を見直す
画面の明るさは周囲の明るさに合わせ、暗すぎたり明るすぎたりしないように調整します。
文字サイズを大きくしたり、コントラストを調整したりすることも、見やすさを向上させ目の負担軽減につながります。
ちなみに、筆者は夜20時になると「おやすみモード」に変わるよう設定しています。
体感になりますが、以前より目の疲れが軽くなった気がするので、iPhoneユーザーかつ目の疲れに悩んでいる方にはおすすめですよ。
3-2. ブルーライトカットを取り入れる
スマホの設定やブルーライトカットメガネ・フィルムは、光量を抑えるのに役立ちます。
特に夜間の使用では、睡眠の質低下を防ぐ助けにもなります。
しかし、最新の研究では、ブルーライトカット眼鏡に眼精疲労を防ぐ効果は認められていないため、過度な期待はせず、軽減策の一つとして活用しましょう。
3-3. 画面との距離・姿勢・照明を見直す
画面は目から40cm以上離し、画面上端が目線と同じかやや下に来るように調整するのが理想です。
作業中は背筋を伸ばし、リラックスした姿勢を保ちましょう。
室内の照明は画面に反射しないように調整し、集中できる環境を整えることが大切です。
ただ、会社員の方だと社内の照明を一個人の意見で変えにくいと思うので、せめて自宅の照明を整えてみてはいかがでしょうか。
3-4. 意識的にまばたきする
意識的にまばたきを増やすように心がけましょう。
特に集中していると感じたら、意識的に「パチパチ」とまばたきを挟むことで、涙が目の表面に行き渡り、乾燥を防ぐ効果が期待できます。
4. 視機能向上も目指せる!効果的なビジョントレーニング
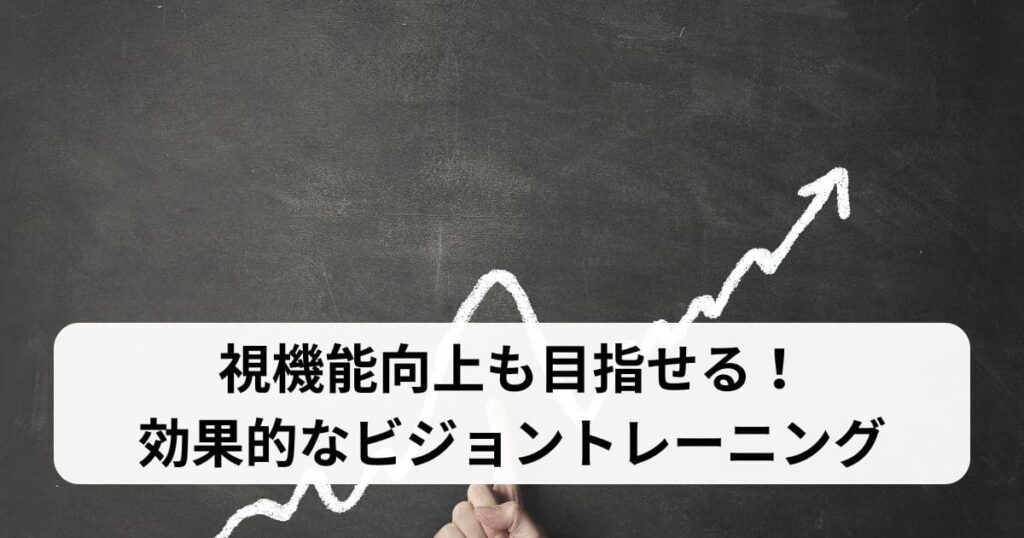
目の疲れ改善に加え、目の機能そのものを高めたい方には「ビジョントレーニング」がおすすめです。
4-1. ビジョントレーニングとは? 目の疲れ改善と視機能向上の関係
ビジョントレーニングは、目の動きをスムーズにし、ピント調節機能や両眼視機能(両目で物を見る力)を高めるトレーニングです。
これにより、目の疲れ軽減に加え、視界のぼやけやピントのずれの改善、読書スピードの向上、集中力の維持といった効果が期待できます。
4-2. 自宅でできる!簡単ビジョントレーニングを紹介
日常生活で手軽にできる方法を以下にまとめました。
| 項目 | 説明 |
| ピント調節トレーニング(遠近トレーニング) | 人差し指を立て、指先と遠くの景色を交互に見る。 |
| 眼球運動トレーニング | 顔は正面に向けたまま、鼻で大きな「〇」を描くように視線を動かす。 |
いずれも無理なく、リラックスして行いましょう。
4-3. トレーニングを続けるためのポイントと注意点
効果を最大限に引き出すには継続が大切です。
毎日2分でもかまいませんので習慣化を目指してみてください。
無理に行うとかえって目を傷める可能性もあるため、目に心地よい刺激を与えるように行うことが重要です。
痛みを感じたら中止し、必要であれば専門家に相談してください。
5. 深刻化する前に知っておきたい「眼精疲労」のサイン
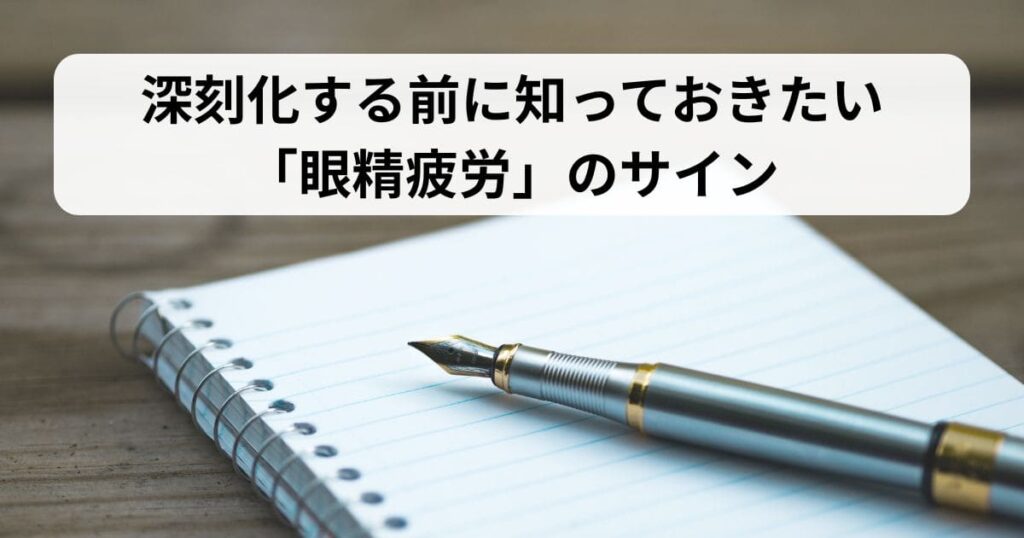
目の疲れが慢性化すると、「眼精疲労」へと移行する可能性があります。
5-1. ただの疲れ目との違いは? 眼精疲労の主な症状
眼精疲労は、十分な休息をとっても回復しない目の疲れや、それに伴う様々な症状の総称です。
目の痛み、かすみ、充血、涙目、まぶしさを感じやすいといった直接的な症状のほか、以下のように全身の不調を伴うこともあります。
- 頭痛
- 肩や首のこり
- 吐き気
5-2. 眼精疲労が引き起こす「全身症状」に注意!
目の疲れは、首や肩の筋肉の緊張を招き、肩こりや首のこり、さらには自律神経の乱れを引き起こして頭痛や吐き気、イライラ感などの精神的な不調につながることもあります。
そのため、決して油断せず、症状が続く場合は医療機関に頼ることをおすすめします。
5-3. 放置すると危険? 眼精疲労が悪化するとどうなる?
眼精疲労を放置すると、以下のリスクを高める可能性があります。
- 視力低下の進行
- 乱視の発生
- 目の病気
また、集中力の低下や仕事の効率低下を招くこともあるため注意が必要です。
まとめ
パソコンやスマートフォンは便利なツールですが、使い方次第で目に大きな負担をかけます。
セルフケアや予防策、ビジョントレーニングを日々の生活に取り入れることで、目の疲れを軽減し、長期的な目の健康維持、そして視機能の向上も期待できます。
まずは、できることから一つずつ意識して実践し、クリアで快適な毎日を送りましょう。
最後にセルフケアやビジョントレーニングなどで改善が見られない場合、あるいは気になる症状がある場合は、専門家への相談を検討してみてくださいね。
以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。
■参考:
vol.152 体内時計に影響する「ブルーライト」
厚生労働省 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン
小児のブルーライトカット眼鏡装用に対する慎重意見 – 日本眼科学会
第一三共ヘルスケア 眼精疲労の原因
日本眼科学会 小児のブルーライトカット眼鏡装用に対する慎重意見


